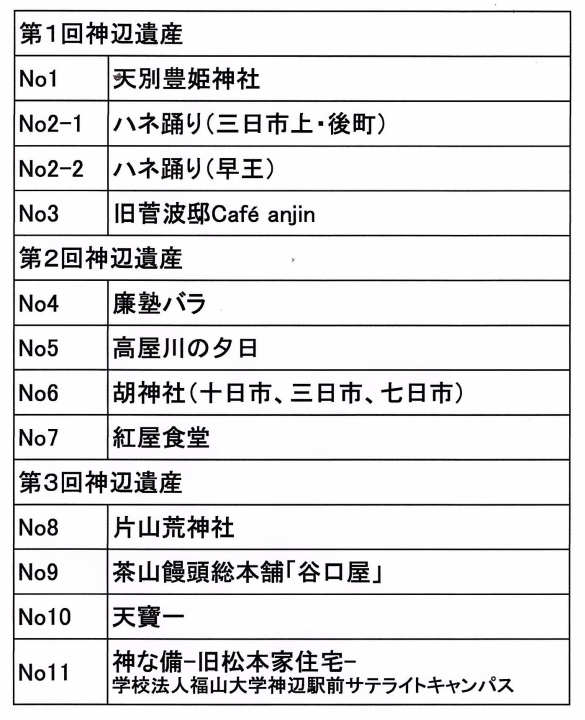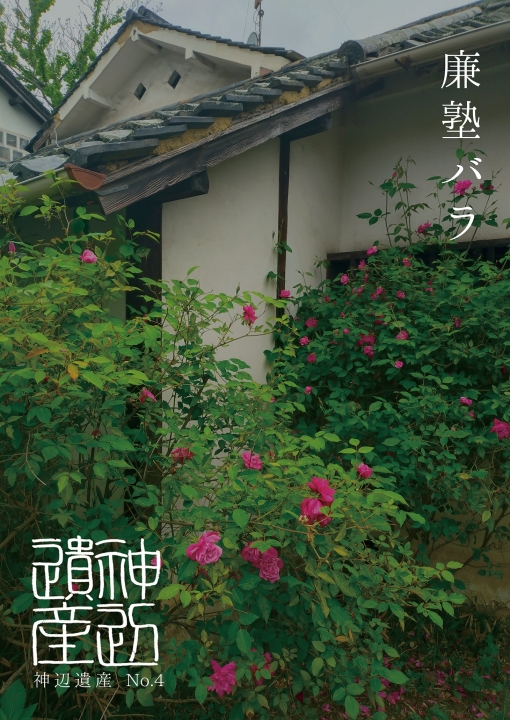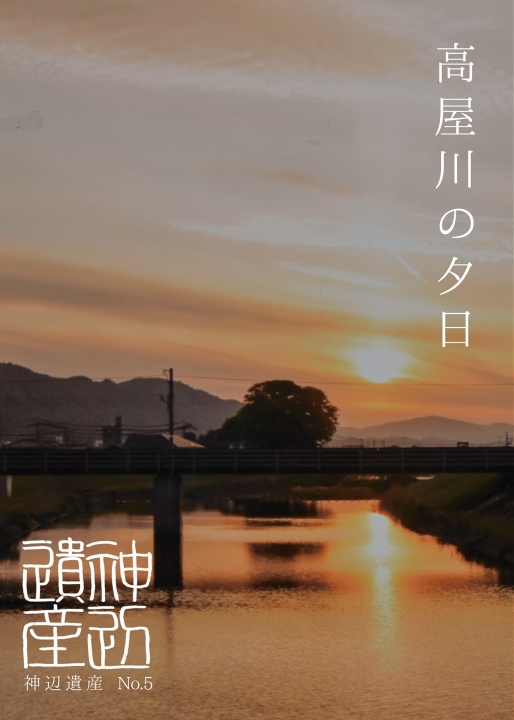神辺遺産の認定
HOME > 神辺遺産制度による賑わいと活力あるまちづくり事業 -神辺遺産制度- > 神辺遺産の認定
第2回 神辺遺産の認定(2024.9.27)
6月10日、第2回神辺遺産選定委員会を開催し、推薦のあった4物件と新たに1件を追加した計5件を選定し調査委員会に諮問(調査依頼)した。9月23日、調査委員会の審議結果の報告を受け、9月27日、「神辺遺産認定委員会」は、第2回神辺遺産として4件を認定した。
認定No4 廉塾バラ(生態系・植物)
認定No5 高屋川の夕日(自然・景観)
認定No6 胡神社(十日市・三日市・七日市)
認定No7 紅屋食堂(食文化・歴史的建築物)
選定案件の荒神社については、地域に多く存在しており、資料不足・調査不足で「暫定候補」として次回選定委員会で再審議となった。
認定式は、11月16日(土)開催の第7回地域遺産フォーラムの中で行う。
●認定4 廉塾バラ
国特別史跡「廉塾ならびに菅茶山旧宅」の中門前で、庚
申バラの一種が「発見」 された。古文書などから、菅
茶山が見たバラとも考えられる。地域住民はこれを「廉
塾バラ」と名付け、2024年6月には「廉塾バラを愛する
会」を結成して継承体制を整えた。各地で接ぎ木や挿木
の講座が頻繁に開催され、旧街道沿いや小学校、駅前な
ど地域各所に植栽されている。廉塾バラを通じて、地域
住民が地域を思い自ら動く機運も醸成されつつある。
●認定5 高屋川の夕日
領家橋付近で、鉄道(鉄橋)と高屋川に夕日が溶け込む
風景は、多くの画家や写真家らの心をとらえる。市指定
天然記念物である「早田荒神社のムクノキ」を背景に、
神辺の原風景の1つとして人々の記憶を喚起する。葛原
しげる作詞の名歌「夕日」は、生家(現在の神辺町八尋
)あたりの風景とされるが、これを思い起こさずにはい
られない。現実と心像が混沌として、1つの「神辺」を
物語る風景であり、認定物件に相応しい。なお、神辺遺
産制度で重要な継承主体を明確にすることはできないた
め、ここで、神辺遺産の趣旨に概ね同意する人として、
「神辺人(かんなべびと)」を提唱し、これを継承主体
として設定した。
●認定6 胡神社(十日市・三日市・七日市)
胡(恵比寿、戎など)信仰は日本全国各地にあり、様
々に祭事が執り行われる。経緯は伝承のみで不明なこ
とが多いが、商売繁盛をはじめ、地域安全、家内安全
などを願い、広く地域住民に親しまれている。旧西国
街道神辺宿では江戸期の三市にそれぞれ祠が残り、年
に一度の例祭が行われる。各祠は江戸期から続くと考
えられね修理を重ねたり、移設されたりしているが、
三者三様の組織をもち、それぞれの形と思いで今に継
承している。同じ民間信仰である荒神社と結びついて
維持されている。旧街道沿いの商店は少なくなったが、
現代生活に沿う形で3つが揃って継承されている。
●認定7 紅屋食堂
旧街道沿いで唯一昭和中期から一般向けに営業を続け
る大衆食堂で、大正期の2階建ての蔵を改築したもの
である。なまこ壁と白漆喰の建築は神辺宿の典型であ
る一方、正面の窓配置は独特である。1953(昭和28)
年に現当主の先代が屋号(由来不明)と店舗を引き継
いだ。「中華そば」や持ち帰りもできる「関東煮」が
が名物であり、現在二代目当主(1953年~)と三代
目(2000年~)が昼夜営業を続けている。地域にお
ける古建築の存在可能性を示すとともに、地域の食文
化を今に伝える貴重な物件である。年代を問わず地域
の人々の胃袋を掴み続けている。
認定No4 廉塾バラ(生態系・植物)
認定No5 高屋川の夕日(自然・景観)
認定No6 胡神社(十日市・三日市・七日市)
認定No7 紅屋食堂(食文化・歴史的建築物)
選定案件の荒神社については、地域に多く存在しており、資料不足・調査不足で「暫定候補」として次回選定委員会で再審議となった。
認定式は、11月16日(土)開催の第7回地域遺産フォーラムの中で行う。
●認定4 廉塾バラ
国特別史跡「廉塾ならびに菅茶山旧宅」の中門前で、庚
申バラの一種が「発見」 された。古文書などから、菅
茶山が見たバラとも考えられる。地域住民はこれを「廉
塾バラ」と名付け、2024年6月には「廉塾バラを愛する
会」を結成して継承体制を整えた。各地で接ぎ木や挿木
の講座が頻繁に開催され、旧街道沿いや小学校、駅前な
ど地域各所に植栽されている。廉塾バラを通じて、地域
住民が地域を思い自ら動く機運も醸成されつつある。
●認定5 高屋川の夕日
領家橋付近で、鉄道(鉄橋)と高屋川に夕日が溶け込む
風景は、多くの画家や写真家らの心をとらえる。市指定
天然記念物である「早田荒神社のムクノキ」を背景に、
神辺の原風景の1つとして人々の記憶を喚起する。葛原
しげる作詞の名歌「夕日」は、生家(現在の神辺町八尋
)あたりの風景とされるが、これを思い起こさずにはい
られない。現実と心像が混沌として、1つの「神辺」を
物語る風景であり、認定物件に相応しい。なお、神辺遺
産制度で重要な継承主体を明確にすることはできないた
め、ここで、神辺遺産の趣旨に概ね同意する人として、
「神辺人(かんなべびと)」を提唱し、これを継承主体
として設定した。
●認定6 胡神社(十日市・三日市・七日市)
胡(恵比寿、戎など)信仰は日本全国各地にあり、様
々に祭事が執り行われる。経緯は伝承のみで不明なこ
とが多いが、商売繁盛をはじめ、地域安全、家内安全
などを願い、広く地域住民に親しまれている。旧西国
街道神辺宿では江戸期の三市にそれぞれ祠が残り、年
に一度の例祭が行われる。各祠は江戸期から続くと考
えられね修理を重ねたり、移設されたりしているが、
三者三様の組織をもち、それぞれの形と思いで今に継
承している。同じ民間信仰である荒神社と結びついて
維持されている。旧街道沿いの商店は少なくなったが、
現代生活に沿う形で3つが揃って継承されている。
●認定7 紅屋食堂
旧街道沿いで唯一昭和中期から一般向けに営業を続け
る大衆食堂で、大正期の2階建ての蔵を改築したもの
である。なまこ壁と白漆喰の建築は神辺宿の典型であ
る一方、正面の窓配置は独特である。1953(昭和28)
年に現当主の先代が屋号(由来不明)と店舗を引き継
いだ。「中華そば」や持ち帰りもできる「関東煮」が
が名物であり、現在二代目当主(1953年~)と三代
目(2000年~)が昼夜営業を続けている。地域にお
ける古建築の存在可能性を示すとともに、地域の食文
化を今に伝える貴重な物件である。年代を問わず地域
の人々の胃袋を掴み続けている。